遠山風土記

『若旦那のお便り』は、あんなもんですが、『遠山風土記』は、遠山常民大学に学んだ地元の写真家「遠山信一郎」さんのエッセイで、遠山郷の神々の由来や民俗風習を著しています。 村の少年少女の「郷土教育」のテキストにも使われています。
「遠山風土記」の中から許可を得て一部ご紹介します。
「遠山風土記」転載文章
庚申講
庚猿の日の楽しみ
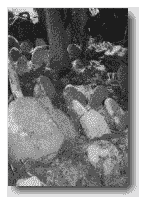
小道木 百体庚申塚
子どものころ、五円玉を握りしめ、「庚申講」に行きました。昭和二十五年ころのことです。当時講を組織していたのは七軒で、その家の子どもたちが二ヶ月に一度、庚申(かのえさる)の日の夕方、宿に当たった家にお金を持って集まりました。
宿は輪番制で、庚申さま(青面金剛像=せいめんこんごうぞう)の掛け軸を床の間に飾り、だんごと酒を供え簡単におはらいしたあと、だんごやちいちのまんま(味ご飯)などを食べたりして夜遅くまで楽しく過ごしました。
和田町内にはほかにも何組かの講がありましたが、このような子どもの祭りではなく大人の祭りでした。
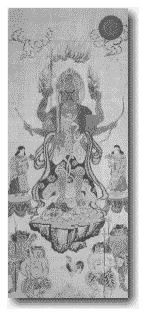
青面金剛の掛け軸
庚申講は、昭和三十年代まで全国各地 で盛んに行われており、仏教では帝釈天(たいしゃくてん)か青面金剛を、神道では猿田彦(さるたひこ)をまつっていました。講には家単位で加入し、血縁関係とか隣組、あるいは有志で組織されていました。
庚申講は、道教(どうきょう)の影響によるところが大きく、修行道士(しゅぎょうどうし)は、庚猿の日を守庚申(もりこうしん)といい、徹夜で修行しなければならないとされていました。それは庚猿の夜には、三戸(さんし=道教でいう人の腹の中にすんでいるといわれる3匹の虫)が寝ている体から出て天に昇り、天帝(天帝)にその人の罪悪を告げられるからだと信じられていたからです。
平安時代、貴族の間で庚猿の日に酒食の宴を催す風習がおこり、それが庚申講として民間に広がったものと考えられています。
室町時代末期になると、各地で庚申供養等が建てられるようになり、申待(さるまち=庚申待ともいい庚申祭りの意)が、猿の信仰と結びついていきました。
その結果、三戸の虫が三猿(さんえん)に置きかえられ、見ざる・聞かざる・言わざるにことわざが生まれたといわれています。
忘れられた庚申講ですが、和田地区で復活したところもあり、また下和田地区では、現在も女性たちにより講が続けられています。
七夕の花くばり
◇和田では、昭和四十年ころまで「花くばり」
 八月七日は七夕祭り。
八月七日は七夕祭り。
六日の朝、山から笹竹をきり、里芋の葉の露を集め墨をすり、短冊に星の名や願い事を書きます。
里芋の露で書くと字が上手になるといわれ、早起きをして一生懸命露を集めたものでした。
竹に、願いをしたためた短冊を付け玄関先に飾り、そのかたわらにむしろを敷き机を置いて、その上に野菜や果物のほか、キュウリやなすに足を付けトウモロコシの毛を尾にした馬を供えました。
また、勉強ができるようにと、本や教科書を置いたりもしました。
和田では、七夕の行事として昭和四十年ころまで、子どもの間で花くばりが行われていました。
この風習は、いつごろから始まったのか不明ですが、山から採ってきた草花や、家で栽培した花をお互いに交換しあうものです。主に女の子の遊びでしたが、昭和三十年代、花がおもちゃや漫画本に変化していったころから、男の子も参加するようになったようです。
この花くばりに特に関心もなかったのですが、あるとき、花くばりにはどんな意味があるかと聞かれたことがあり、調べてみましたら、実は和田以外では見あたら ない、大変めずらしい行事【飯田市美術博物館・桜井弘人(さくらいひろと)さんの話】だったということがわかりました。
水野都沚生(みずのとしお)氏は、『秘境伊那谷物語』の中で、この花くばりのことを次のように書いています。
「・ハタを織ったその布の美しさを見せあった形の名残が花に変移した。・篠(ささ)につける短冊は本来衣服を吊るしたものから色紙に変わったものだからその美しい模様をくらべたことから花に変移した。・花は、「草木染め」の染料の素として摘花(てきか)したもので、織りあげた布を染めた昔のしきたりが形だけ花として残ったもの」
いずれにしても、子どもの遊びだった花くばりは、女性の重要な仕事のひとつだった裁縫(さいほう)や機織(はたおり)と深い関係があったことはたしかなようです。
七夕祭りは、日本古来からの棚機女信仰(たなはたづめしんこう)に、中国の星祭り(乞香奠=きっこうてん)が習合(しゅうごう)したもの(仏教民俗辞典)といわれ、江戸時代に農耕儀礼や祖霊信仰色(それいしんこうしょく)の濃い形で民間に広まりました。
また、飾りは正月の松飾りと同じ神の依代(よりしろ)であり、七夕は単なる星祭りでなく、祖霊祭りである盆行事のひとつであったのではないかと考えられています。
夏の夜、夕涼みをしながら、空に横たわる天の川の牽牛(けんぎゅう)と織り姫(おりひめ)の変わらぬ愛を思い、ロマンにひたってみるのもいいものです。
飛騨鰤(ひだぶり)
◇普通の家庭の年取り魚はサンマかイワシ
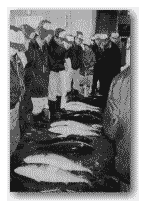
富山市氷見漁港ブリ市 (撮影 沢田 猛 氏)
大晦日にはよそで働いている子どもたちも帰省し、年取をします。
南信濃村では年取り行事は早いほど良い、とされていましたが、最近ではほとんどの家庭で夕方から夜にかけて行われるようです。 そして、食卓には宅配便で取り寄せた大きなカニ、町で買ってきた寿司や刺身が並ぶ。昆布巻きやタツクリ、黒豆、お菜など本来の年取り料理はすみに追いやら れ、すっかり忘れられようとしています。
それでも、年取り魚「ブリ」は今でも主役です。
明治の中ころ、越中氷見(えっちゅうひみ)では旧暦十一月末、能登など富山湾で水揚げされた寒ブリの腸を出し中をきれいに洗い、甘塩にこしらえます。塩ブリ四本を竹籠(たけかご)に入れむしろに包んで一行李(ひとこうり)、四行李約三十二貫(かん)が一荷(ひとに)となり「越中ブリ」として各地に出荷されました。 むしろには、今の標章に当たる店の印を墨で書き入れられました。
越中ブリは、馬方により二泊三日で飛騨高山へ運ばれ、番所となっている「川上問屋(かわかみどんや)」を経由し飛騨一円・信州・美濃へと送られました。
信州へは、牛方により野麦峠を越し松本へ、もうひとつは木曽の薮原(やぶはら)から権兵衛峠(ごんべえとうげ)を越し伊那谷へ入ったのです。
川上問屋へは約八千行李、すなわち三万匹前後のブリが入り、一行李三銭の運上金(うんじょうきん)が明治政府の収入になったそうです。
遠山へはもうひとつのルート、下呂(げろ)から馬籠(まごめ)、妻籠(つまご)、大平峠(おおだいらとうげ)を経由して飯田へ入り、さらに伊那山脈を越し、運ばれてきました。
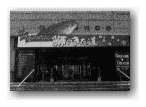
松本市で開催された
「鰤のきた道」展
2001年 12月
こうして運ばれたブリは、信州に入り「飛騨鰤」と呼ばれ、高値で売買されました。 一方糸魚川(いといがわ)から塩の道を運ばれ、大町地方に入ったブリは糸魚川ブリと呼ばれていました。
甘塩の越中ブリに比べ腸を洗わずたくさんの塩をふるため、価値も低かったそうです。
明治十九年ころ、旧暦の十二月四・五日ころ氷見を出たブリは、上穂(うわぶ(現在の駒ヶ根市))へは二十日ほどかかって着き、米一石(いっこく)【=百升(ひゃくしょう)】が二円八十銭のころ、一匹一円四・五十銭で売られていました。
富山の問屋(ブリ屋)は、仕入が1匹約二十八銭、仕込み賃や上納金、運び賃を支払い、一行李で一円五十銭の利益があったそうです。
今でも高いブリ。このころ遠山郷では、振り一匹いったいいくらしたのでしょうか。とても普通の家では買えなかったのではないでしょうか。
明治の終わりころ、越中での浜値(はまね)は「一斗(いっと)ブリ」といって、米一斗がブリ一本というのが相場でした。
ところが信州では「一俵(いっぴょう)ぶり」といわれ、約四倍の高値がつけられていた(『鰤街道』)と記されています。

松本市で開催された 「鰤のきた道」展
『ふるさとへの伝言』の中には、こう書かれています。「正月は、サンマを半分ずつ、どっちが大きいかくらべて横目でにらんでとる」デイサービスに通うお年寄りたちに聞きますと、当時はたいへん貧しかった、と口をそろえていいます。
野牧(のまき)シゲ子さん(大正八年生まれ)は八歳のとき、諏訪(すわ)へ子守り奉公に行かされたと涙を浮かべて話されました。
一方では、コンニャクや養蚕(ようさん)、煙草(たばこ)、勝栗(かちぐり)で財をなした人や、山師(やまし)相手の商売で稼(かせ)いだ人が多くいたことも事実です。
こうした一部の人が飛騨鰤を食べられ、普通の家庭の年取り魚はサンマかイワシでした。 霜月祭りに、必ずサンマがだされるのはサンマは晴れの日の一番のごちそうだったからなのです。
(注)遠山郷へは、青崩峠(あおくずれとうげ)を越えて入ってきたブリもあり、飛騨鰤とはいいませんでした。
営林署の山の神
◇山の仕事は危険が多かった

梨本貯木場
1995 年3月
木沢梨元(きざわなしもと)、営林署貯木場の山つきに木の鳥居があり、そこに山の神がまつられています。
この山の神は大山祗神社(おおやまつみじんじゃ、(注)「祗」は、正確には、示辺に氏と書く)といい、下條村にある入登山神社(にゅうとざんじんじゃ)から分祀(ぶんし)したもので、大山祗命(おおやまつみのみこと)をまつり、山作業の安全を祈願しています。
大山祗命は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の子で、大山津見神とも記し大山祗御祖命(おおやまつみおやのみこと)ともいい、山を主宰(しゅさい)し、山神を統率する神ですが、愛媛県越智郡(おちぐん)大三島町の大山祗神社では水軍の守護神として信仰を集めました。
遠山郷は広大な山林を有し、木材の宝庫として江戸時代には榑木(くれき)を年貢として搬出していましたが、明治二十九年には王子製紙が共有山林の伐採を始 め、昭和三十五年ころまで和田の町は林業景気にわいていました。

営林署の山の神
(大山祗神社)
この山林業務にたずさわる人たちは、山師(やまし)・杣(そま)・ヒョウなどと呼ばれていましたが、彼らは山へ入るときはいろいろな行事をして、山での災難除け(さいなんよけ)をしていました。
山の神をまつり、御神酒(おみき)を奉じておはらいをしたり、赤い紙と白い紙を重ねて三角に折り、それを棒にさして山の所々に立てたりしました。
また毎月一日と十五日は仕事を半日で終え、山の神をまつり安全を祈ったりもしました。
それほど、山の仕事は危険が多かったことも事実で、営林署でも大勢の方が山で命を失いました。
その霊をなぐさめるためと、安全を祈願するため、営林署は毎年四月十四日と七月十四日にこの大山祗神社で例祭を行っています。
(注)営林署の山の神は、平成13年3月に事務所に隣接する敷地内に移転しました。
祭りを伝えた修験者
◇遠山の霜月祭りと修験道
遠山の霜月祭りと修験道(しゅげんどう)とは、切っても切れない縁があるといわれています。
霜月祭りの原点、湯立て神楽(かぐら)を伝えたのは修験者で、日本各地にさまざまな影響を与えています。
とくに神楽や田楽など民俗芸能の多くは、明治の神仏分離令(1868年)により見えにくくなっていますが、実は修験者の芸能だった(五来重=ごらいしげる・宗教学者)といわれています。
「花 祭り」で有名な愛知県三河の地方には、祭りは修験者によって始められたという言い伝えがありますが、民俗学者で遠山郷ではなじみが深い武井正弘(たけい しょうぐ)氏によれば、「天竜水系には平安末期から鎌倉中期にかけて熊野修験(くまのしゅげん)が来訪流入し、花祭りはそうした熊野修験がもたらし創り出 した祭り」だと結論しています。
霜月祭りで行われる湯立ては修験者の作法によってなされ、「九字(くじ)」を切り、印を組み神々を勧請(かんじょう)するという一連の動作は、修験道そのものです。
和 田の霜月祭りのクライマックスである「面」の登場の前に、太夫(禰宜=ねぎ)が火伏せの神事を行いますが、そのとき唱える呪文(じゅもん)は「臨(り ん)・兵(へい)・闘(とう)・者(や)・皆(かい)・陳(ちん)・烈(れつ)・ 在(ざい)・前(ぜん)」で、これは道教にルーツを持つ、修験の代表的な秘法のひとつです。
修験道は、和歌山県の葛城山(かつらぎさん)で呪禁道(じゅごんどう)の修行をしていた役小角(えんのおづぬ)が開祖といわれています。
役(えん)の行者とも呼ばれる役小角は、7世紀飛鳥時代に実在していたことはたしかなようですが、修験道の開祖、役行者とは別個の、理想化された修験道の祖師であるといわれています。
平安時代、律令制(りつりょうせい)の崩壊により、出家僧が激増し、彼らは山岳地域に進出、呪術(じゅじゅつ)を習得していきました。
このころ、紀伊半島の南端熊野地方あるいは越前白山で修験する密教僧が大きな勢力を蓄え、原始的な山岳信仰は密教修験道の基礎になっていきました。
山岳で修行をつんだ、空海は真言宗を、最澄(さいちょう)は天台宗をおこし、多くの一般民衆の支持を得、山岳仏教は盛んになっていきました。
日本は山の国。 山は、金鉱師、木地師(きじし)、杣人(そまびと)、炭焼きなど山人(さんじん)あるいはなぞの漂白民サンカと呼ばれる集団が、古代から明治にいたるまで 日本の山地、山岳に存在していました。
山人は、神武東征(じんむとうせい)の際征服され山に追われた先住民で、支配の網から逸脱していったため、里人(さとびと)からは鬼・天狗・山男・山姥(やまうば)などと恐れられていました。
これら山人に関する記録はほとんど残ってい ませんが、日本の山岳宗教が山人との深い結びつきの上に成立したことはたしかなようです。
修験者は、こうした山人との交流により、金属文化をとり入れ、護摩あんど火を操る技術を習得していきました。
また、昭和初期まで遠山地方であったクダショウ憑(つ)きを追いはらった禰宜とか、拝み屋さんとかいわれる民間祈祷師は、山伏の息災護摩、調伏法(ちょうふくほう)、憑き物落としなど加持祈祷の影響が強く、密接な官営にあるといわれています。
蔵王権現(ざおうごんげん)の不動明王(ふどうみょうおう)を崇拝する修験者は、仏教・神道(しんとう)からは「雑宗」と呼ばれ低俗視されながらも、日本全国の山々を巡り、自分たちの宗教と文化を小さな村にまで広げていったのです。
畑の名称
◇山を開拓してきた歴史

名古山ヤズカ畑
遠山郷は、中央構造線上にあって地形が急峻で、田はもちろん畑を開墾するにも大変な苦労をしてきました。
木を切り、根を掘りおこし、石を拾い、すこしずつ、少しずつ開梱していきました。
先人たちは、日当たりの良い、少しでも平らなところは田や畑にし、住む家はそのすみの方に建てました。
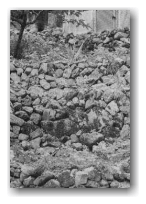
梶谷ツジ畑
名古山(なごやま)にヤズカ畑と呼ばれるところがあります。それは、畑をうなぐ(耕す=たがやす)ときに出たイシックラ(小石・石)を捨てたところで、ヤズカとは、石垣・石堤(いしづつみ)のことで、名古山の畑のクロ(周り)には畑からでた石が高く積み上げられています。
また漆平島(しっぺいじま)の畑はゼリ畑と呼ばれています。
名古山ヤズカ畑。遠山では、小石のたくさんあるところをゼリックラといいますが、漆平島の畑はたいへん小石が多いのでそう呼ばれたのです。
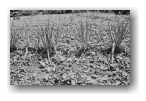
漆平島ゼリ畑
そして梶谷(かじや)にはツジ畑と呼ばれているところがあります。
ツジとは、ツイジカケからきた言葉と思いますが、ツイジは石垣のことで築地と書きます。
やはり開梱のときに出た石を積み上げ、畑を作っていったのです。
他にも石塚などもありますが、いずれもサガシ(斜面)の。それも石の多い土地を開墾し、耕地していった先人たちの苦労が偲(しの)ばれ地名がそのことを物語っています。地名からそこの歴史がわかります。 地名は、歴史です。
青崩峠
◇秋葉街道・・・諏訪信仰の道

青崩峠から遠山郷を望む
八重河内小嵐(やえごうちこおらし)の民宿島畑(しまばた)に残されている明治十五年の「宿泊人名簿」には、毎日五~六人の宿泊者の行き先が「秋葉山(あきはさん)」と書き記されています。
これからも当時の秋葉詣でに、いかに多くの人たちが秋葉街道を行き来したかが伺(うかが)われます。
秋葉街道は、古くは「諏訪道」と呼ばれ、諏訪信仰の道として発達していきましたが、近世に徳川家康の庇護(ひご)により全国で遠州秋葉山の火伏鎮護(ひぶせちんご)の神への信仰が高まり、いつしか「秋葉街道」と名を変えていったのです。
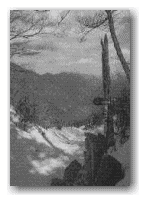
青崩峠
その信仰の道は塩の道であり、霜月祭りを伝えた文化伝播の道、さらに武田信玄によって軍用路として利用された道でもありますが、杖突(つえつき)、分杭(ぶんぐい)、地蔵など幾つもの峠越えのある険しい道のりでした。その難所のひとつが「青崩峠」(標高1082m)です。
青崩峠はその美しい眺望とは対照的に、中央構造線(メディアンライン)の大規模な断層によりガレとなり、名前の由来となった青色のむき出しの山肌は、往来する旅人に恐怖感さえ与えていました。
加藤陶綾(とうりょう=画家・歌人、著書に「信濃画帳」他。故人)は「青崩の目指す岩嶺(いわみね)見え居つつ幾時ぞいまだ谷登り居る」(池田寿一編『遠山紀行』)と、峠への道の険しさを詠(うた)っています。

米山吉松碑
青崩峠は、遠州と信州の国境にあり、地質、動植物の生態、民俗学の他、歴史的にも重要なところです。
そこに明治二十五年建立され、すっかり忘れられた一基の石碑があります。飯田事件に関わりがあったのでは(『遠山物語』)、といわれている米山吉松(松雨=しょうう)の碑文です。
「・・・・ 病往来為嫌然於青崩嶺難不甚高倹悪而蜀道不啻也、松杉之外草木不繁茂焉多石礫而景至天然其名巌々大者如厦屋・・・・ 明治二十有五稔一月信南江儀之荘米山松雨撰並書」(原文の一部)「往来するには病気になるほど険しいと嫌われた青崩峠は、それほど高いところではない。た だ険悪な道だけでなく、石ころが多く松や杉のほか草木も茂らないところで、その景観は天然のままで、大きな岩は家ほどもあり、奇妙な形は鳥獣の様に見える」とこのように峠の様子が書かれています。
青崩峠は、ロマンの霊犬早太郎(れいけんはやたろう)伝説の陰に、悲しい歴史がありました。
大正から昭和にかけて、十五歳前後の少女たちが貧しい家族を助けるため、期待と不安を抱きながら峠を越えて行きましたが、その少女の多くは、製糸工場の 劣悪で過酷な労働に病し、肺結核に冒されていったのです。生家で養生できた人はまだまだ良い方で、峠を生きて越えられなかった少女もおり、青崩峠は、まさ に女工哀史(あいし)の峠でもあったのです。
古くは太平洋側の塩を、そして諏訪の文化を遠州に、遠州からは都の文化を信州へ伝播した、青崩峠。 青崩峠は、信仰の道秋葉街道とともに、また歴史を語る信州と遠州の「国ざかい」として、いつまでも人々の心に残ることでしょう。
(8)遠山氏の祖先は鉄鋼の技術集団か
◇遠山氏の祖先・・・?

畑上の白山神社
松山義雄氏著による『新編伊那風土記』に、霜月祭り、谷京(やきょう、焼尾=やきお)峠、白山信仰のことが詳しく書かれています。
その中で注目したいのは、白山神社の神像が隻眼(せきがん=片目)であるということです。
松山氏によれば、その御神体伊邪那岐命(ごしんたいいざなぎのみこと)、大穴牟遅命(おおあなちのみこと)は鉄神であり、風越山(ふうえつざん)一帯を中心 に、これらを信仰する産鉄民(さんてつみん)集団が生活していたのではないか、そして、その集団の一部が遠山郷へ入り、遠山氏の祖先となったのではない か、と書かれています。
さて、白山信仰は、山鉄民集団が各地に鍛冶業(かじぎょう)を求めて移り住み、全国に広まったといわれていますが、遠山にある白山神社について調べているうちに、ちょっと不思議なことに気がつきました。
それは、上島(かみじま)・畑上(はたかみ)・十原(とっぱら)・名古山(なごやま)の四つの白山(城白山=しろはくさん)神社の地域には、そこにしかない苗字があるということです。
例えば、上島には、今川(いまがわ)・山下・上野・陰佐(かげさ)・宇佐美。畑上には、平沢。十原には、坂本・山口・石堂(いしどう)・城崎(しろさき)・荒井・皆浦(みなうら)。
名古山には、柴原・小西・中村などです。時代を遡ったりして、もう少し正確に調べなければなりませんが、十原では苗字が皆違うことも併せて、白山信仰と何か関わりがあると思われます。
松山氏は、屋敷氏神(うじがみ)として全国各地でまつられている白山神社が、漂白民である産鉄集団の信仰と深い関係にあると想像しています。
霜月祭りは、舞処(まいどころ)は炉の形であり金山彦神(かなやまひこがみ)も現れるので、本来の意味を亡失した鉄山関係の宗教行事、とも書かれており、遠山氏の祖先は鉱山師と深い関わりがあったのでしょうか。
遠山信一郎著/遠山風土記より







